昨年末に「バーチャルユーチューバー」の存在がクローズアップされて以降、日本国内ではバーチャルキャラクターが八百万神の如く生まれ続けている。その中で今回は「東雲めぐ(しののめめぐ)」という、今年3月にデビューしたばかりのバーチャルキャラクターに注目したいと思う。
すでに東雲めぐちゃんの生放送配信を見ている人は気づいているかもしれないが、彼女はほかのバーチャルキャラクターと違う存在感を醸し出している。「日常」という平凡な言葉を使ってしまえばそれまでだが、彼女には「彼女自身の日常」を視聴者に意識させる魅力がある。「東雲めぐちゃんは日本のどこかで生活している」と、彼女の実在感を見ている人たちは錯覚してしまうのだ。
そんな存在感はどこからどのようにして生まれているのか? その疑問に答えてくれる人たちが今回のインタビューの主役である。「東雲めぐ」の魔法を存分に語ってもらえたので、前後編の2つに分けてお届けしたいと思う。
インタビュー: 田村 幸一
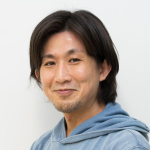
三上 昌史
広告業界での紙面デザインを経て、2002年に専務取締役として株式会社シーエスレポーターズを設立。現在はアニメとITを使ったBtoC事業「Gugenka®」の事業統括として、ビジネス周りから企画、全体のクオリティの部分まで、プロデューサーを担当している。
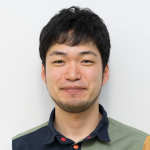
室橋 雅人(MuRo)
デザイナーとしてゲーム開発を経験、アニメーションやコンポジットを得意とする。 現在は株式会社エクシヴィに所属。VR制作のディレクターをしている。 個人では「クリエイティブな人を増やすVR」をテーマにVR作品を制作している。主な開発は『MakeItFilm』『PlayAniMaker』。

近藤 義仁(GOROman)
株式会社エクシヴィ代表取締役社長。2010年エクシヴィを創業。2013年Oculus Rift DK1と出会い「これからはVRの時代が来る」と確信。Oculus Japanチームの立ち上げに携わる。ロートデジアイ初音ミクVR LIVE、刀剣乱舞VR三日月宗近Ver.等キャラクター×VRコンテンツを数多く手がける。今年VRアニメ制作システムAniCastを発表。
田村
AniCastの話に移っていきたいと思いますが、Unityで作っていく上で良かったなと思うところはありましたか?
室橋
率直に、Unityはアニメ表現しやすい印象です。リアルタイムで、レンダリングしたいものに迫る表現まで高められるのはゲームエンジンのいいところですね。
田村
逆にこういうことができたら良かったのにな、ということはありますか?
室橋
カメラに対してのアニメ表現的なパース変化ですね。多分、アニメ業界もしたいと思っているはずです。
田村
そのあたりはUnityではまだできない?
室橋
いや、できるんですけど、リアルタイムにしたいんですよ。「アニメの中に入りました」じゃなくて、「その世界はアニメです」というVR空間をやりたくて、そのためには、リアルタイムでアニメと相違ない感覚まで高める必要がある。たとえば、奥から何か向かってくるとき、アニメには緩急がありますよね。工数をかければ表現できるんですけど、本当にオート処理にするとすれば、補正をバンバンかますというか、細かく場合分けされたルールをいっぱい盛り込まないといけない。その辺り、構想中ではあります。

田村
AniCastは室橋さんが開発したPlayAniMakerをベースに誕生したと思いますが、PlayAniMakerからAniCastに進化していくときに気をつけたところはありますか?
室橋
前提条件としてずっとあるのは「楽しむ」ことなんです。作ることを楽しんだ結果、何かができていたらいいねというものだから、PlayAniMakerはわりと作る事に寄っているんです。一方AniCastでは「アイドルをつくりあげる」というのがベース設計にあって。だから仕草一つとっても嘘くさくならないようにしなくてはならない。「(キャラクターの)形ができてOKか?」というとそうではなくて、人間は常にアイドリングしているとか、そういう自然な仕草をどれだけ盛り込み続けるかです。演じる人の負荷にせず、やったことを自然に補正して、キャラクターに落とし込む仕組みをつくっていかなければならないんですね。
田村
そういう知見にいつぐらいから気付いていましたか?
室橋
VR開発を始めた最初の頃からですね。3D感っていうのが昔から嫌いで、それをいかに消すかをずっと考えているんです。3Dのアニメ表現は3ds Maxのトゥーンシェーダーの出始めの頃からずっとやり続けているんですよね。研究が3D ソフトからUnityに代わって、でも結局やっていることは同じです。
今回は中に人が入るっていうところで、どうやって着ぐるみを着ている感じを消すかというのがすごく重要なポイントです。存在にしたいんですよね。「アニメの」っていう括りがない、というか。「もしかしたら本当にいるのでは?」っていうぐらいの存在にしてあげるのが目標です。
近藤
気配を持つんですよね。生きているって多分「動き」「所作」なんですよね。めぐちゃんは動いてない面がほぼないというのが強いです。そこが躍動感だったり、アニメーションの原点であって。逆に、動いてないから着ぐるみ感が出る、着ぐるみのショーを見ているみたいな感じになっている。
田村
バーチャルキャラクターを作っているほとんどの皆さんはUnityを使っていますが、同じUnityで開発していても、そうした違いは出てきてしまう?
近藤
Unityでやりやすくなったことではあるけど、もうUnityであるかどうかは関係ないんですね。物事とか人間を本質的に見る力とか、観察力の問題だと思います。だから常に観察して、それをフィードバックしています。それがすごく細かいことなので、なぜこんなに生き生きしているのか気づけないくらい自然になっている。めぐちゃんを見たあとに他を見て「なんだろう、この差分は?」みたいなふうにはなると思います。
田村
でも、AniCastや東雲めぐちゃんを見てそういうノウハウが分かってくると、いよいよそういうクオリティで競争する時代になってくるのでは?
近藤
そこは別に自由だとも思っています。たとえば「にじさんじ」さんの委員長(=月ノ美兎ちゃん)は話が面白いし、手が動かなくても成立していて。多様性があってそれはそれでいい。めぐちゃんは生き生きしているというコンセプトで際立っているだけで、全員が目指せというわけではないですね。
三上
めぐちゃんという存在が面白いのは、室橋さんが言ったみたいに「本当にいるのでは?」って思った瞬間に、日常が彩られるところです。普段の日常ってそんなに面白いことが起きるわけじゃないですけど、たとえば空から女の子が降ってきたりとか、非現実が地続きになった瞬間、VRとリアルが一緒になったときに、もっと幸福度が上がるのかなと感じたんですよね。僕らがやっている取り組み自体が、人間にとって価値あることなんじゃないかな?って、なんとなくここ最近感じられました。
近藤
気配をつくるというのは多分、日本人は昔からすごく得意で、江戸時代の妖怪とかってまさにバーチャルユーチューバーの原点みたいなところありますよね。「ガシャガシャうるせぇから、これは座敷童のせいだ」とか。擬人化したりキャラ化するのは多分、しょうがないですよね。八百万神みたいな。
田村
気配を感じるのが得意なんでしょうね。つくるのもそうだけど、感じるのが得意。
近藤
そこは東洋的であると思いますね。だからアメリカ人がリアルアバターにいくのはなんとなくわかります。宗教的な背景も大きいじゃないですか。なので、AniCastみたいなアプローチが全然ウケない国も絶対あると思いますし、真似する国もあると思います。
田村
実際AniCastが運用フェーズに入って、思ったとおりうまくいったというところと、想定外だったみたいなところというのはありますか?
室橋
想定外はいっぱいありますよ。
田村
「(バーチャルギフトの)タワーが何本建ったら止まっちゃう」とか?
近藤
他のSHOWROOM配信でのギフトっていうのは、あんなにいっぱい来ないんですよ。有名アイドルの配信者でも少しずつ来て、最後イベントで満足したときに盛り上がってくるんですけど、めぐちゃんは初っ端から降り続けたんです。その辺はある程度予想していたのでストレステストができる環境に構築したんですけど、システム的にやはり対処しきれなかった部分ですよね。

東雲めぐのSHOWROOM配信では、バーチャルギフトとしてタコやタワーなど、VR空間上に物を贈ることができる。
室橋
終わってから(SHOWROOM・CTOの)佐々木さんに問い合わせしたら「こういう処理を入れてください」って教えてもらったりとか。
近藤
SHOWROOMさんって外部向けにAPIを出していないから、僕らは与えられた分で頑張ってたんですけど、佐々木さんからしたら「あ、これ叩けばいいんですよ」みたいな…。”開発あるある”ですけどね(笑)。
田村
実際にサーバーサイド+ブラウザ環境とクライアントアプリケーション環境では、処理実装が全然違うし。
近藤
面白いのが、Twitterとかで反響を見ていると「それは機能実装できる」という項目があるんです。たとえばファンアート機能がなかったので、とりあえずめぐちゃんがOBSで工夫してやっていると、誰かが「この機能、(AniCastの)中に入れてあげてください」って言ったりとか。「じゃあ、入れようか」って機能追加して。
田村
そういう意味では、視聴者が望んでいたことは、わりと想定の範囲内ではあったんですか?
近藤
実は、要望として挙がっているほぼ全ての機能はやるつもりでタスクを積んであったんですけど、ファンの人が求めているものをなるべく優先するようにしています。毎朝配信というのはすごく良くて、アップデートして反応を見てというPDCAが回っています。生配信だから多少トラブルはあるかもしれない。それって普通の大手企業さんから下請けしていたら絶対NGですよね。たとえば、この前の生配信では8分ほど止まりましたけど、そんなの下手したら損害賠償っていう話でしょ? でもその辺はチャレンジに重きを置いているし、見ている人もそれを理解してくれているというのは、いいと思いますね。
三上
今回の取り組みというのは、そういう挑戦がすごくやりやすい関係性ですね。
田村
そこは三上さんも含めてですけど「作っている人たちの情熱が最優先にされるべき」みたいな哲学を感じますね。
近藤
お金とクリエイティビティなら、トレードオフが発生すると思うんです。われわれどうしても、クリエイティビティに重きを置いているので。でも長い目で見れば、マネタイズメソッドはいっぱいあるわけじゃないですか。
たとえば、その気になればギフティングをムチャクチャやらせる施策をうてるわけですよ。「タワーゲーム!」「タワー10本欲しいっすー」みたいなキャラを作って(笑)。でもそれは短期間での稼ぎ方ですよね。それはめぐちゃんでは違うなと思ってます。

田村
ここまで話を聞いていると、ここにいる皆さんがやりたいと思っていることって、新しいアニメーションの形なのかなって思うんですよね。今の日本のアニメは声優さんの知名度も重要な要素の一つですが、めぐちゃんは声優さんの知名度が重要な要素でなく、むしろ匿名を是としている感じがしている。今の日本のアニメとはちょっと違うものを目指しているのかなと思うんですが、どうでしょうか。
近藤
おっしゃるとおりですね。これまでのアニメ制作のパラダイム(見方・考え方)って紙に描く手法の延長線上じゃないですか。作画・原画がいて、すごい大変で。一方で、CGアニメーションでもモーションキャプチャーしたりとかはすごい金がかかるし。
でもVRを理論に取り入れると、そこを変えられる。Unityだったら、ポストエフェクトでカラーグレーディングできるし、被写界深度調整ができるし、リアルタイムでポスプロダクションもできるし、プリプロダクションもできる。ほぼ1個のツール内で、VRを使うとさらに完結していくような恐ろしい効率化が起こる。パラダイムシフト前夜みたいな感じなんですよ。
三上
その最前線にいるのがめぐちゃん。めぐちゃんは今後たぶん、学校行きました、カラオケ歌っていますっていうのを自撮りして放送していくし、それを編集して1個の日常系アニメを作れるポテンシャルを秘めているわけです。
田村
私が東雲めぐちゃんのプロジェクトを最初知った時、プロジェクトの最終ゴールにアニメ放送があって、SHOWROOMやYouTubeはそのプロモーションとしてやっているのかなと思っていたんですよ。でも、SHOWROOMの配信を見ていて「ひょっとして、SHOWROOMでやっていることそのものが実はアニメなのでは?」って思ったんですね。だから「東雲めぐ」プロジェクトでのアニメーションという言葉の定義と、世の中が思っているアニメーションの定義、いわゆるテレビアニメとは…。
近藤
違うんです。そもそもアニメーションというのは、魂が入って何かが動くっていうこと、絵が動いてそこに躍動感を感じるということですよね。それがなんとなくアニメと訳され略されていって、本来の意味・定義を失っていって、みんな「アニメ」=「テレビアニメ」で30分枠の放送だと思っている。製作委員会があって、プロデューサーが入って、ディレクターが着いて、キャスティングされてみたいな、ウォーターフォールモデルで作るのがみんなの常識じゃないですか。でも、もうビジネスとして成り立たなくなってきている。本来、何がしたかったんですかね? という問題提起でもあるんですよ。テレビアニメ化とかCDデビューっていうのに華やかなイメージがあったのは、多分昭和なんですよ。でももうそれは違っていて。より多くの人に届けるのが成功なんです。今の女子高生はCDプレイヤー持ってないから、楽曲をCD化するほうが成功するチャンスが狭くなっている。もう状況が全然変わっているのに、まだまだ変わっていない。
三上
両社の方向性がだいたい合致しているのが、ここのプロジェクトの良さですよね。他社さんからお話いただくときって、どうしてもテレビアニメ化をゴールに見据えたVTuberっていうのがあるんですけど、僕らが向いているのはそこではなくて、今やっていることがアニメという定義なんです。
近藤
何と言うか、今の視聴形態とか枠組みにとらわれすぎているんだよね。もう平成終わるのに、昭和メソッドじゃないですか。Unityは、その昭和メソッドをほとんどぶち壊しましたよね。
田村
リアルタイムエンジンでできる可能性って、まだまだあると思いますか?
近藤
メチャクチャありますよ。しかも既存の制作ツールとの差がなくなってきている。使う人が増えているから圧倒的に知見がたまっていきますよね。
近藤
未来を予測すると、今は(バーチャルキャラクターの)バブルだからお金を投資するところが出てきて、プロダクションとかメッチャ増えたじゃないですか。ビジネスが広がるのは別にいいけど、キャラクターは大事にしてほしいよね。
田村
キャラクターを大事にするという話も踏まえて、三上さんのほうから、「東雲めぐ」というキャラクターをどう大事にするかというあたりの展望をお聞かせください。
三上
僕らも楽しんでやれているんですけど、クリエイターさんたちとの関りがすごく強い存在になっていると思うんですよね。二次創作だったり。なので、めぐちゃんの活動を通して作ることが楽しくなったりとか、そういう存在にできたらいいですよね。皆さんの力で拡張されていくというか。
こないだのお誕生日配信で
この1枚を丸々紹介できてなかったので今日の朝に皆さんにお見せしました!皆さんどれも可愛いって癒されてました(*´-`)#めぐあーとお便り は今日の12時まで募集して明日の朝紹介します✨今日も一日 頑張りましょうね☺️?
私も学校行ってきます??♀️✨#東雲めぐ pic.twitter.com/NSV6AA0m5J— 東雲めぐ@4/25(水)朝7:30〜SHOWROOM配信♪ (@megu_shinonome) 2018年4月10日
田村
そういう力はやはり重要ですか?
三上
重要だと思いますし、逆に今後僕らが気をつけなければいけないのは、皆さんがつくってくれたコンテンツをどうリスペクトして扱っていくのかというところですね。めぐちゃんをきっかけに何かを作って表現したいって人が増えて、一緒にこの世界を拡張できたら嬉しいなって思います。
近藤
ファンを大事にしつつ。

田村 幸一
2010年ごろよりUnityを使い始め、2013年のUnite Japanでは個人開発に関する講演を行う。2017年にユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社にコミュニティエバンジェリストとして入社し、PR業務などを担当している。東雲めぐちゃんデビュー2日目の朝配信で東京タワーをギフティングした古参めぐるーまー。

春から高校1年生♪ カラオケと可愛いものが大好きです! 平日朝7:30〜、日曜夜19:00~、SHOWROOMで生放送! 誰でもライブ配信ができる人気サービス「SHOWRO…