さあ今日も、仕事が終わった後の楽しいゲーム開発の仕事だ。
エディターを開き、コードを書きながらうんともすんとも言わないステージ・ギミックのコンポーネントを睨みつける。
私は兼業型個人ゲーム開発者だ。
ゲーム開発の傍ら、様々なゲーム開発者向けサービス・ツールの販売を手伝うコンサル業で生活している。
ゲーム開発者としては、目下『Back in 1995』のアップデート版、そしてニンテンドー3DSシリーズ版である『Back in 1995 64』に向けて開発続行中だ。ステージを追加したり、難易度を追加したり、ボイスを追加したりと細かな改修を行っている。いくらかのトラブルによりアップデート版の開発が当初計画からかなり遅延してしまっているが、どうかご辛抱いただきたい。
Made with Unity日本版の開設を聞いて、今一度『Back in 1995』にまつわるルーツと思想、そして今後について考える良い機会だと思った。そこで、忙しい手を止めてこの文章を書いている(いや、手は動かしているが)。
発表当時の背景
およそ2年前の2015年4月10日、私は『Back in 1995』の制作発表と、ほんの短いトレイラー映像を初公開し、思いつく限りのゲームメディアの窓口にプレスリリースを送りまくった。 このゲームの奇抜さには自信があったし、実は多少の怒りのパワーも交えながらのプレス資料作りは楽しいものだった。何を隠そう、発表日は「Unite 2015 Tokyo」の3日前であったからだ。そして、私はこのUniteに公募を提出して落選していた。
事情を知っている人は多いかもしれないが、『Back in 1995』はもともと、PlayStation Vita向けに開発されていた。その当時はPlayStation Mobileというインディー専用のストアがあり、個人でもVita向けゲームが開発できたのだった。
私はすでにミニゲームを1タイトルPlayStation Mobileストアにリリースしていたため、Unite 2015 Tokyoでは、その経験をもとにコンソールゲーム機展開のテーマで公募書類を提出した。そして、講演の場で新作として『Back in 1995』の制作発表をしようと考えていたのだ。残念ながら公募は落選し、追い打ちのように、そのすぐ後にPlayStation Mobileサービスは終了してしまった。
しかし、『Back in 1995』をUnite 2015 Tokyoのタイミングで世の中にお披露目する計画は変えなかった。イベントがあると人が集まる。人が集まると今ホットな情報について話し合うものだ。それをねらった。
ありがたいことに、国内・海外さまざまなメディアに『Back in 1995』の制作発表取り上げられることとなった。個人的には「Kotaku」「Destructoid」「Siliconera」といったインディーゲームに強い海外メディアに取り上げられたことが嬉しかった。私は有頂天だった。

ドライブに残っていた中で、最も古いスクリーンショットがこれだ。この時はまだ、キャラクターの上半身が完成していなかった!
なんせ、当時は誰も「初代PlayStation世代のビデオゲームの感触」を目指したゲームなんて、気にも留めていなかったからだ。
ニュー・エイジ・オブ・レトロゲーム
『Back in 1995』のプロジェクトがスタートした直後の話をしよう。多くの開発者から、「なぜこの題材を選んだのか?」と聞かれることがある。私はいつもシンプルに、私が初代PlayStationが好きだったことと、いまだかつて誰もチャレンジをしたことがないジャンルだったから、と答えている。
私が広義のゲーム作りに対していつも漫然と思うのは「なぜみんな、同じことをやってしまうのか?」ということだ。同じようなRPG、同じようなアクションゲーム、同じようなカードゲーム。もちろん、ファンの多いジャンルに対して新作が供給され続けることは重要だし、旬を逃したジャンルは、その語り手がインディーに託される場合もある。
しかし「同じこと」をやりながらプレイヤーの注目を集めるためには、どうしてもボリュームやクオリティ、完成度、IPの強さなどに依存してしまう。こうした部分は、いざ大手ゲーム開発スタジオがそのフィールドに参入してきたときに太刀打ちできないだろう。
個人ゲーム開発者としては、もっと既存のゲームシステムを改良したり、2つのシステムを合体させたり、あるいは睡眠不足のさなかのオフィスで見た白昼夢から、見たことのなかったゲームのアイディアを取り出すことが個人ゲーム開発者の特権だと思っている。膨大な顧客分析やマーケティングに基づいた課金導線の設計を考え抜くのは企業にまかせよう(それはそれで価値のある仕事だと思っているが)。
たとえば、自作のPlayStation Vita向け『CardBoard Cat EP』というタイトルでは、背面タッチパネルを背面的に(全面的に)使ったアクションゲームだ。Vitaにしかないハードウェアギミックを積極的に使っているタイトルが少ないように感じたため、それに依存した新しいゲームシステムを提案した。過去に類似タイトルがあるのかもしれないが、少なくとも私は「新しい触り心地のゲーム」になったと思っている。

さて、このタイトルが終わった直後に思いついたテーマが「初代プレイステーションの質感に立ち返る」というものだった。
世の中にはピクセルアート愛があふれている。ドット絵は文化で、どんどん進化しているし、若いファンもどんどん増えている。またサウンド面でもチップチューンはジャンルとして確立している。私もそうしたイベントでグッズを買い、ピクセルアートのゲームをプレイすることが大好きだ。 しかし、私自身のゲームの趣味が爆発したのは初代PlayStationからだった。初期ポリゴンゲームがゲームの原体験である私にとっては、「なつかしい」とはちょっと違う感覚だったのだ。こうした時代のものから、「価値を見出せないか?」と思い立ったのである。つまり『Back in 1995』は実験なのだ。
実験、実験、実験…
私が見たい映像を作り出すには、たんにローポリにするだけでは全く不十分だ。そこで、開発初期はいろいろな実験に明け暮れた。特に、プラットフォームをPCに転向してからは「より汚いグラフィック」を目指すことが可能になった。具体的なグラフィクスのテクニックについてはブログに記しているのでそちらを参照いただこう。 これ以外の話でいえば「メニュー画面の洗練されていない感じ」「十字キーオンリーの操作体系」「血しぶきエフェクト」あたりに当時感を出せる工夫をしている。

血しぶきのエフェクト
没になったアイディアとしては「メモリーカードの再現」がある。これは、ソフトウェア上でメモリーカード(に近しいシステム)を再現し、スロットに刺してセーブする…というようなものだ。

没にしたセーブ画面
労力のわりに効果が薄いこと、プレイヤーが混乱しそうであることを踏まえて、このアイディアは没にした。そうして最初のステージ、最初のギミックなどが形作られてきた。
困難の時
さあ、システム側の実験はできた。ゲームの作りこみだ!! 私が初めて長編ゲームにとりかかって気が付いたことは、私はシナリオ作りが大変苦手だということだ。なんてこった! シナリオ開発は遅々として進まなかったが、無い知恵を絞りながら、どうにか2時間程度のプレイを目指してシナリオを構築した。発売後の「ボリュームが物足りない」というコメントについては、その通りだと思っている。もし私に財力があってシナリオ担当を雇っていたら、プレイ時間は倍以上にできたと思う(その場合は価格も倍にせざるを得ないのだが)。
あまりにプレイヤーを待たせすぎないためにも、2016年4月のローンチまでにできる限りの要素を追加した。しかし、開発終盤の時期は、ちょうど私が未来を賭けていた事業がうまくいかなかった時期でもあり、精神的にボロボロだった。『Back in 1995』の評価の厳しさは、そうした切羽詰まった状況と、私の開発スキル不足に起因があると考えている。
単純な見込み違いもあった。『Back in 1995』の難易度が低すぎる、という意見についてだ。このタイトルで様々なインディーゲームイベントに出展したが、皆一様に「難しすぎる」と言っていた。私は最後まで体験してもらうことを重視し、難易度調整をした。しかし配信後は逆で、「簡単すぎる」という意見が多かった。これは、展示会に参加するタイプのプレイヤーと、Steamでコメントを送ってくれるプレイヤーの層の違いによるものと考えている。アップデートでそうした部分をなるべく改修するつもりだ。
タイトルについて
実は、このゲームのタイトルは初めから『Back in 1995』ではなかった。”初代PlayStationの質感を目指す”というミッションは変わらなかったものの、当初は『A Life Across The Rooftops』という(今考えるとだいぶん冗長な)タイトルとして開発を進めており、ステージ構成も建物の屋上を渡り歩く構造になっていた。
ティーザーサイトを構築するとき、このゲームが提供する体験を端的に示したドメインをとろうと考えていた。そこで取り出したワードが「1995年に立ち返ろうー Back in 1995」だった。
私はこのディーザーサイトのURLを何度も見るうちに、短くゲームのテーマを端的に示しているな、と考えるようになった。そして、そのままタイトルを変更した。
ちなみに、『Back in 1995』には限定的にディスク版を作ろうというアイディアもあった。何と、『Back in 1995』の発表と時を同じくして、初代PlayStationの特徴的なブラック・ディスクを、マリリン・マンソンが自身のアルバム「The Pale Emperor」に採用したというニュースが入ってきたからだ。2015年の時点でも、工場はひそかに温存してあったわけだ!

パロディ・グッズの試作
ディスク版は在庫リスク等の都合により話が流れたが、将来的にこのレベルまでチャレンジするディベロッパーも今後現れるだろう。
『Back in 1995』で示したことと、これから。
初代PlayStationのような「ローポリ」ではない「レトロポリゴン」にも独自の価値があるはずだ、というテーマをゲーム開発者へ投げかけることはできたと思う。実際、2016年はレトロポリゴンを意識したタイトルが少し増えた年になった。日本のインディーゲームクリエイターからもレトロポリゴンを題材にしたゲームが現れることを切に願う。
ゲーム開発という文化には、光る価値があるにもかかわらず、隣接するジャンルの盛り上がりが大きすぎて、意図せず存在が隠れてしまっている「何か」がまだまだ埋まっている。
それは、おそらく万人受けしない。世代や文化圏の隔たりで「そんなものに価値はない」と叩かれることもあるだろう。しかし、そのクリエイティビティを心から待ってくれているプレイヤーも必ず存在する。私はこれを「狂気」と表現している。
私が次に何かを作る場合も、その発掘作業がテーマになることはおそらく間違いないだろう。
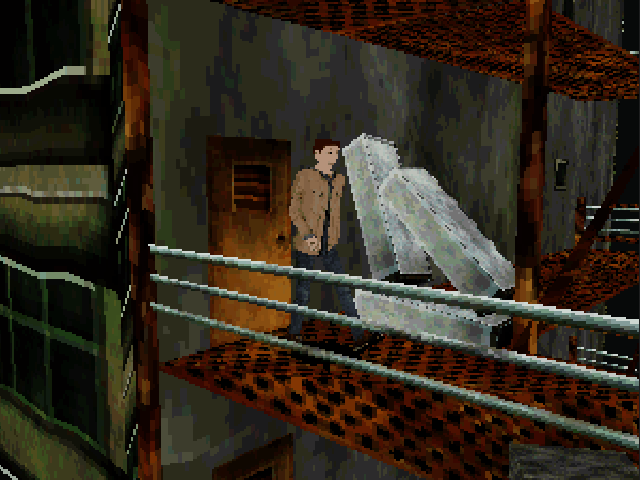
お気に入りのgifアニメ
おまけ
作者が収集したレトロポリゴンゲームの「手触り」まで再現しようとしているゲームリスト
方々で言っているが、私は日本からレトロポリゴンの「RPG」「格闘」が出てほしいと願っている!協力は惜しまない。









